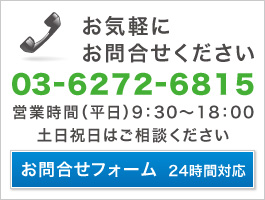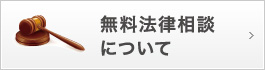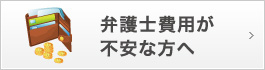Author Archive
デジタル遺言書について
先日、法制審議会(法相の諮問機関)がパソコンなどで作成した「デジタル遺言書」の導入に向けた制度案を近く取りまとめるとの報道がありました。証人の立ち会いと録画を要件に、自筆での記述や押印なしでも遺言を作成できるようにするのが柱のようで、中間案を取りまとめてパブリックコメントにかけ、2026年を目途に関連法の改正を目指すようです。
現在の遺言書は原則として自筆証書、公正証書、秘密証書での作成が求められていますが(特別の方式による場合を除く)、自筆証書遺言の場合は、民法上作成の要件が定められており、また公正証書遺言の場合は公証役場での手続が必要となります。
近時は法務局での自筆証書遺言書保管制度ができるなど遺言書制度が進化しておりますが、デジタル遺言書はこの流れを加速させるものとなるように思われます。各種の遺言書制度ができることで、ご自身の思いを確実に遺すことができるようになるでしょうから、積極的に遺言書制度を活用していきたいものです。
<参考・自筆証書遺言書保管制度>
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

東京千代田区・文京区の小野貴朗総合法律事務所は、JR水道橋駅徒歩2分の身近な法律事務所です。
関東一円を中心に、ご相談により全国の皆様をサポートしております。
不動産トラブル(建物明渡請求、借地借家)、遺言・相続、交通事故、離婚問題から、成年後見、債権回収、企業法務まで、個人・法人を問わず幅広く対応いたします。
特に、不動産・相続・交通事故・離婚などのご相談は初回30分無料です。
公認会計士、税理士、司法書士など他士業との連携で、複雑な問題もワンストップで解決に導きます。
あなたに寄り添い、笑顔を取り戻すために全力を尽くします。
法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続における2025年問題
2025年問題がネット等で話題になっております。これはいわゆる団塊世代(1947~1949年生まれの世代・合計出生数が約800万人)が2025年までに後期高齢者(75歳以上)となるため、医療、介護、年金等の様々な分野で問題が生じることをいいます。
この2025年問題は、相続においても影響を及ぼすと考えられております。高齢者が増加することにより相続の発生が増加することも予想され、それに伴い遺産分割の対応が必要になってきます。相続税の基礎控除額が下がりましたので、相続税対策を検討するご家庭も増加すると考えられます。
亡くなった高齢者に相続人がいない場合は、所謂空家問題が発生することも考えられますし、子どもがいない夫婦の一方が亡くなった場合は、亡くなった人の兄弟姉妹との相続問題が発生する場合もあります。縁の遠い兄弟姉妹やその子が当事者となることで話し合いが円滑にいかない場合も生じております。兄弟姉妹の相続の場合は相続人の人数が増える場合があり、場合によっては相続人の数が二桁に及ぶこともあります。そうなると任意の話し合いで協議をまとめるのは難しくなってきます。
ただ、兄弟姉妹の相続の場合は、生前に遺言書を作成しておくことで、兄弟姉妹に相続させないようにすることができます。後に残される配偶者に苦労をかけないようにしておくのも夫婦の役割と言えるでしょう。あの時遺言書を書いておいてもらえればと亡くなった後に後悔しても手遅れですので、ご自身が亡くなった後のことをどうしたいかを遺言書に残しておくことをお勧めします。
また、遺言書を書いておくことで、残された相続人が遺産を把握するのが容易になります。一人暮らしをしていた人が亡くなった場合、残された相続人は自宅のタンスなどを開けて預金通帳などがないかを探すことになりますが、最近ではネット銀行もありますので、その場合は預金通帳が出てこないこともあります。そうするとせっかく銀行に預金があるのに発見できないまま見逃されてしまうということも考えられます。
ですので、ご自身の遺産をしっかりと相続人に承継させるためにも、どこにどのような財産があるのかを遺言書に残しておくことが必要です。遺言書を公正証書にしておけば、相続発生後に相続人が公証役場で検索することもできるので、遺言書を見つけてくれることも期待できます。
おひとり様の場合は亡くなった後に葬儀の手配や自宅の後処理等をしてくれる人を確保することも必要でしょう。亡くなった後に自宅の後処理をする人がいないと空家問題が発生し、近隣に迷惑がかかってしまいます。先祖代々のお墓を管理しているようであれば墓じまいを考えることも必要でしょう。
このように相続においても様々な問題が発生することが予想されておりますので、後でトラブルにならないよう事前に各種専門家に相談するのが得策といえるでしょう。弊所では、税理士、司法書士等の隣接士業とのネットワークがございますので、ご自身の家庭で思い当たる点があるようであれば、早めにご相談ください。

東京千代田区・文京区の小野貴朗総合法律事務所は、JR水道橋駅徒歩2分の身近な法律事務所です。
関東一円を中心に、ご相談により全国の皆様をサポートしております。
不動産トラブル(建物明渡請求、借地借家)、遺言・相続、交通事故、離婚問題から、成年後見、債権回収、企業法務まで、個人・法人を問わず幅広く対応いたします。
特に、不動産・相続・交通事故・離婚などのご相談は初回30分無料です。
公認会計士、税理士、司法書士など他士業との連携で、複雑な問題もワンストップで解決に導きます。
あなたに寄り添い、笑顔を取り戻すために全力を尽くします。
法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
離婚等の人事訴訟や家事調停におけるウェブ会議の活用
これまで家事調停では、協議を行う期日等ではウェブ会議等を利用して手続を行うことはできるものの、ウェブ会議等を利用して離婚や離縁を内容とする調停を成立させることはできませんでした。また、人事訴訟においても、ウェブ会議等を利用して離婚や離縁を内容とする和解を成立させることはできませんでした。
しかし、近時の法改正により、人事訴訟や家事調停において、ウェブ会議を利用して離婚等の和解・調停を成立させることができるようになりました。この法改正は令和7年3月1日から施行されております。
ただし、ウェブ会議を利用することができるのは、裁判所(調停委員会が行う家事調停の場合は調停委員会)が、ウェブ会議を用いて参加することを希望する当事者や相手方の意見を聴いた上で相当と認めたときになります。また、和解や調停を成立させる最終的な段階の期日は音声だけでなく映像の送受信ができることが必要になりますので、電話で参加することはできません。
これにより、当事者は裁判所に出頭することなく手続に参加することができるようになりますので、裁判所までの出頭に要する交通費や時間の負担が軽減され、裁判制度を利用しやすくなったといえます。当事者によっては、相手方が同じ裁判所の建物内にいるだけで苦痛を感じるということもありますので、その場合は依頼した弁護士の事務所からウェブ会議に参加することで、裁判所に出頭する苦痛を減らすという対応も考えられそうです。
なお、この法改正では、人事訴訟等の家庭裁判所等における訴訟について、当事者が公開の法廷で行われる「口頭弁論」にウェブ会議を利用して参加することもできるようになりました。
〈参考URL〉
https://www.moj.go.jp/content/001431813.pdf

東京千代田区・文京区の小野貴朗総合法律事務所は、JR水道橋駅徒歩2分の身近な法律事務所です。
関東一円を中心に、ご相談により全国の皆様をサポートしております。
不動産トラブル(建物明渡請求、借地借家)、遺言・相続、交通事故、離婚問題から、成年後見、債権回収、企業法務まで、個人・法人を問わず幅広く対応いたします。
特に、不動産・相続・交通事故・離婚などのご相談は初回30分無料です。
公認会計士、税理士、司法書士など他士業との連携で、複雑な問題もワンストップで解決に導きます。
あなたに寄り添い、笑顔を取り戻すために全力を尽くします。
法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
遺産分割協議の期限について
これまで遺産分割については時的制限がなかったため、相続人が早期に遺産分割の請求をすることについてインセンティブが働きにくいとされていました。しかし、相続開始後遺産分割がないまま長期間が経過すると、生前贈与や寄与分に関する書証等が散逸し、関係者の記憶も薄れることになります。そうすると、具体的相続分の算定が困難になり、遺産分割の支障となるおそれがありました。また、遺産分割がされないまま二次相続が発生したり行方不明の相続人が出てくること等により相続が複雑化するという事態も起きるようになります。
そこで、相続開始の時から10年を経過した後にする遺産分割は、法定相続分での分割となるとされました(ただし、10年経過前に相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をしたとき等の例外はあります)。これにより、早期の遺産分割請求を促す効果が期待されるようになりました。この制度は昨年4月1日から施行されております。
この制度は、改正法の施行前に被相続人が死亡した場合の遺産分割にも適用されますが、その場合は経過措置により、施行時から5年の猶予期間が設けられました(相続開始のタイミングによって異なるパターンあり)。
いずれにしても遺産分割は早めに解決することが肝要といえるでしょう。相続問題が発生したときは早めに弁護士に相談することをお勧めします。

東京千代田区・文京区の小野貴朗総合法律事務所は、JR水道橋駅徒歩2分の身近な法律事務所です。
関東一円を中心に、ご相談により全国の皆様をサポートしております。
不動産トラブル(建物明渡請求、借地借家)、遺言・相続、交通事故、離婚問題から、成年後見、債権回収、企業法務まで、個人・法人を問わず幅広く対応いたします。
特に、不動産・相続・交通事故・離婚などのご相談は初回30分無料です。
公認会計士、税理士、司法書士など他士業との連携で、複雑な問題もワンストップで解決に導きます。
あなたに寄り添い、笑顔を取り戻すために全力を尽くします。
法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
相続登記の義務化について
これまでは相続が発生しても不動産の相続登記は義務ではありませんでした。また、都市部への人口移動や人口減少・高齢化の進展等により、地方を中心に土地の所有意識が希薄化し、土地を利用したいというニーズも低下していました。そのような背景から、土地が相続登記されないことにより所有者不明の土地が発生し、所有者の探索に多大な時間と費用が必要という問題が生じるようになりました。また、共有者が多数の場合や一部所在不明者がいる場合、土地の管理・利用のために必要な合意形成が困難となり、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まず、民間取引が阻害されるなど、土地の利活用が阻害される問題が生じるようになりました。高齢化の進展による死亡者数の増加等により、今後この問題が深刻化するおそれが高まったため、所有者不明の土地の解消に向けた民事法制の見直しがされるようになりました。
その一環として、不動産の相続登記の義務化がされるようになり、今年の4月1日から施行されています。具体的には、相続により不動産を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に所有権の移転の登記を申請しなければならなくなりました。施行日前に相続が発生していた場合は、施行日から3年以内に申請する必要があります。正当な理由がないのにその申請を怠った場合は10万円以下の過料になる場合があります。
もっとも、遺産分割協議が難航するなどして期限に間に合わないときは、簡易な義務履行手段として相続人申告登記制度を利用する方法があります。これは、相続人が、①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である旨を申請義務の履行期間内に登記官に申し出ることで申請義務を履行したものとみなすものです。これにより、相続人が複数存在する場合でも、特定の相続人が単独で申し出ることが可能となります。申出を受けた登記官は、所要の審査をした上で、申し出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記することになります。
相続人申告登記をした後に遺産分割が成立したときは、当該遺産分割の成立日から3年以内に所有権移転登記申請をしなければなりません。ですので、事案の内容にもよりますが、二度手間にならないよう3年以内に遺産分割協議を終えて相続登記をする方が現実的かもしれません。
遺産分割協議も10年という期限が設けられ、相続に関するルールは大幅に改正されております。相続問題が発生した場合は、早めに弁護士に相談することをお勧めします。

東京千代田区・文京区の小野貴朗総合法律事務所は、JR水道橋駅徒歩2分の身近な法律事務所です。
関東一円を中心に、ご相談により全国の皆様をサポートしております。
不動産トラブル(建物明渡請求、借地借家)、遺言・相続、交通事故、離婚問題から、成年後見、債権回収、企業法務まで、個人・法人を問わず幅広く対応いたします。
特に、不動産・相続・交通事故・離婚などのご相談は初回30分無料です。
公認会計士、税理士、司法書士など他士業との連携で、複雑な問題もワンストップで解決に導きます。
あなたに寄り添い、笑顔を取り戻すために全力を尽くします。
法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
越境した竹木の枝の切り取りについて
これまで土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは自らその根を切り取ることができるが、枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に枝を切除させる必要があるとされていました。
しかし、竹木の所有者が枝を切除しない場合は訴えを提起し切除を命じる判決を得て強制執行の手続を取ることになりますが、竹木の枝が越境する都度、常に訴えを提起しなければならないとすると、救済を受けるための手続が過重となりました。また、竹木が共有の場合、竹木の共有者が枝を切除しようとしても、基本的には変更行為として共有者全員の同意が必要と考えられており、竹木の円滑な管理を阻害することになっていました。
そこで、近時の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には枝を自ら切り取ることができるとされることになりました(民法233条3項)。
① 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③ 急迫の事情があるとき
①の場合に共有物である竹木の枝を切り取るに当たっては、基本的に竹木の共有者全員に枝を切除するように催告する必要がありますが、一部の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、その者との関係では②に該当し催告は不要となります。
また、竹木が共有物である場合は、各共有者が越境している枝を切り取ることができるとされました(民法233条2項)。したがいまして、竹木の共有者の一人から承諾を得れば、越境された土地の所有者がその共有者に代わって枝を切り取ることができると考えられます。
所有者不明の土地が増加するにつれて、竹木の枝の処理に関する問題も増加することが考えられます。費用負担の問題もありますので、詳細は弁護士に相談することをお勧めします。

東京千代田区・文京区の小野貴朗総合法律事務所は、JR水道橋駅徒歩2分の身近な法律事務所です。
関東一円を中心に、ご相談により全国の皆様をサポートしております。
不動産トラブル(建物明渡請求、借地借家)、遺言・相続、交通事故、離婚問題から、成年後見、債権回収、企業法務まで、個人・法人を問わず幅広く対応いたします。
特に、不動産・相続・交通事故・離婚などのご相談は初回30分無料です。
公認会計士、税理士、司法書士など他士業との連携で、複雑な問題もワンストップで解決に導きます。
あなたに寄り添い、笑顔を取り戻すために全力を尽くします。
法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
被相続人の上場株式等に係る口座の調査について
遺産分割をするに当たっては、被相続人の遺産を把握することが必要になりますが、被相続人が上場株式等も保有していたと考えられる場合は、その調査も必要になります。
被相続人の自宅に証券会社から年間取引報告書などの書面が届いていた場合は、当該書面を確認して証券会社に問い合わせることで調査可能です。
そのような書面がない場合でも、株式会社証券保管振替機構(通称:ほふり)に対して、上場株式等の口座が開設されている証券会社、信託銀行等の情報の開示請求をすることによって調査が可能です。当該情報の開示結果を基に、各証券会社、信託銀行等に問い合わせることで、上場株式等の銘柄名、取引履歴、保有残高を確認することができます。
詳細については、ほふりのウェブサイトに掲載されております。もしご自身での調査が難しいという場合は弊所で調査を代行することも可能ですので、お気軽にご相談ください。

東京千代田区・文京区の小野貴朗総合法律事務所は、JR水道橋駅徒歩2分の身近な法律事務所です。
関東一円を中心に、ご相談により全国の皆様をサポートしております。
不動産トラブル(建物明渡請求、借地借家)、遺言・相続、交通事故、離婚問題から、成年後見、債権回収、企業法務まで、個人・法人を問わず幅広く対応いたします。
特に、不動産・相続・交通事故・離婚などのご相談は初回30分無料です。
公認会計士、税理士、司法書士など他士業との連携で、複雑な問題もワンストップで解決に導きます。
あなたに寄り添い、笑顔を取り戻すために全力を尽くします。
法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
売買取引の相手方の判断能力低下と取引中止義務について
高齢化社会に伴い、お年寄りの判断能力が低下していることに付け込んで業者が商品を次々に販売する「次々販売」に関する問題が生じております。例えば、高齢者が内装工事業者の訪問を受け、次々と自宅の室内設備交換の契約をしてしまったといった事例があります。
このような次々販売について、近時の裁判例で、販売業者に取引をいったん中断すべき信義則上の注意義務があると判示したものがあります(東京地裁令和2年1月29日判決)。
当該事例は、昭和7年生まれの男性に対して、宝飾品等の販売を行う業者が、平成21年2月から平成28年3月までの間、過量かつ不必要な宝飾品等を繰り返して販売したというもので、男性が業者に対して、かような行為が不法行為を構成するとして損害賠償請求を求めたものです。
裁判所は、売買取引が客観的に買主にとってその生活に通常必要とされる分量を著しく超えた過大なものであったからといって、当該取引が当然に売主の買主に対する不法行為を構成するものではないとしつつも、本件においては業者の認識や男性の判断能力の程度等の事情から、業者には社会通念に照らし、信義則上、男性との取引をいったん中断すべき注意義務を負っていると判示し、その後も取引を継続したことは、社会通念上許容されない態様で男性の利益を侵害したものとして違法と評価されるべきものであると判示しました。
裁判例で判示されているように、業者の責任を問うためには、信義則上の注意義務を認定してもらうことが必要になってきます。被害回復は必ずしも容易ではないので、判断能力が低下している高齢者がいらっしゃる場合は、弁護士に財産管理を依頼する方法や、後見・保佐等の制度の利用を検討し、高齢者の財産確保に努めることが必要です。
弊所では、高齢者の財産管理や、後見・保佐の申立て等も扱っておりますので、お気軽にご相談ください。

東京千代田区・文京区の小野貴朗総合法律事務所は、JR水道橋駅徒歩2分の身近な法律事務所です。
関東一円を中心に、ご相談により全国の皆様をサポートしております。
不動産トラブル(建物明渡請求、借地借家)、遺言・相続、交通事故、離婚問題から、成年後見、債権回収、企業法務まで、個人・法人を問わず幅広く対応いたします。
特に、不動産・相続・交通事故・離婚などのご相談は初回30分無料です。
公認会計士、税理士、司法書士など他士業との連携で、複雑な問題もワンストップで解決に導きます。
あなたに寄り添い、笑顔を取り戻すために全力を尽くします。
法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
当事者の住所・氏名等を秘匿する制度について
令和4年5月18日に民事訴訟法等の一部を改正する法律が成立し、当事者等がDVや犯罪の被害者等である場合に、その住所・氏名等の情報を相手方に秘匿したまま民事訴訟手続を進めることができる秘匿制度が創設されました。民事訴訟手続については、国民がより利用しやすいものにするために総合的な見直しが行われておりますが、氏名・住所等の秘匿制度は令和5年2月20日から施行されています。
具体的には、申立人等は、裁判所に対して、相手方にも秘匿してほしい住所・氏名等を秘匿事項届出書面に記載した上で、秘匿決定の申立てをします。そして、申立人等の住所・氏名等の全部又は一部が当事者に知られることによって当該申立人等が社会生活を営むのに著しい支障を生じるおそれがあることにつき疎明があった場合には、裁判所は住所・氏名等の全部又は一部を秘匿する旨の決定をすることができます(民事訴訟法133条1項)。
秘匿決定がされると、訴状等には、住所・氏名を記載せずに裁判所が定める事項(代替事項)を記載すればよいことになります。また、秘匿対象者以外の者は秘匿事項届出書面の閲覧等をすることができなくなります。
制度の概要については、法務省のウェブサイトでも紹介されております。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00316.html

東京千代田区・文京区の小野貴朗総合法律事務所は、JR水道橋駅徒歩2分の身近な法律事務所です。
関東一円を中心に、ご相談により全国の皆様をサポートしております。
不動産トラブル(建物明渡請求、借地借家)、遺言・相続、交通事故、離婚問題から、成年後見、債権回収、企業法務まで、個人・法人を問わず幅広く対応いたします。
特に、不動産・相続・交通事故・離婚などのご相談は初回30分無料です。
公認会計士、税理士、司法書士など他士業との連携で、複雑な問題もワンストップで解決に導きます。
あなたに寄り添い、笑顔を取り戻すために全力を尽くします。
法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
遺産分割前における預貯金の払戻制度について
被相続人の預貯金については、従前は相続人全員の同意を得なければ遺産分割前に相続人単独での権利行使が認められないとされておりました(最高裁平成28年12月19日決定)。しかし、相続債務を弁済する必要があったり、相続人の生活費等を支出する必要があるなどの理由から、被相続人の預貯金を遺産分割前に払い戻す必要がある場合に不便が生じておりました。
そこで、相続法改正により、相続人が遺産分割前に裁判所の判断を経ることなく、一定の範囲で遺産に含まれる預貯金の払戻を受けることができるようになりました。
各共同相続人が単独で権利行使可能な金額は、以下の計算式で求められる金額となります。ただし、同一の金融機関(同一の金融機関の複数の支店に預金がある場合はその全支店)からの払戻は150万円が上限になります。
口座ごとの相続開始時の預金額×1/3×払戻を求める相続人の法定相続分
払戻の際に必要な書類としては、本人確認書類、印鑑登録証明書のほかに、概ね、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(全部事項証明書)・除籍謄本・改製原戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本(全部事項証明書)が必要になります。ただし、金融機関によって必要となる書類が異なる場合がありますので、金融機関に事前に確認した方が良いでしょう。
本制度により払い戻された預貯金は、相続人が遺産の一部分割によりこれを取得したものとみなされ、後日の遺産分割において調整が図られることになります。

東京千代田区・文京区の小野貴朗総合法律事務所は、JR水道橋駅徒歩2分の身近な法律事務所です。
関東一円を中心に、ご相談により全国の皆様をサポートしております。
不動産トラブル(建物明渡請求、借地借家)、遺言・相続、交通事故、離婚問題から、成年後見、債権回収、企業法務まで、個人・法人を問わず幅広く対応いたします。
特に、不動産・相続・交通事故・離婚などのご相談は初回30分無料です。
公認会計士、税理士、司法書士など他士業との連携で、複雑な問題もワンストップで解決に導きます。
あなたに寄り添い、笑顔を取り戻すために全力を尽くします。
法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。