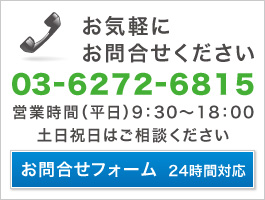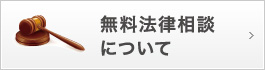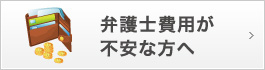Archive for the ‘不動産’ Category
越境した竹木の枝の切り取りについて
これまで土地の所有者は、隣地の竹木の根が境界線を越えるときは自らその根を切り取ることができるが、枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に枝を切除させる必要があるとされていました。
しかし、竹木の所有者が枝を切除しない場合は訴えを提起し切除を命じる判決を得て強制執行の手続を取ることになりますが、竹木の枝が越境する都度、常に訴えを提起しなければならないとすると、救済を受けるための手続が過重となりました。また、竹木が共有の場合、竹木の共有者が枝を切除しようとしても、基本的には変更行為として共有者全員の同意が必要と考えられており、竹木の円滑な管理を阻害することになっていました。
そこで、近時の民法改正により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には枝を自ら切り取ることができるとされることになりました(民法233条3項)。
① 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
② 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
③ 急迫の事情があるとき
①の場合に共有物である竹木の枝を切り取るに当たっては、基本的に竹木の共有者全員に枝を切除するように催告する必要がありますが、一部の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、その者との関係では②に該当し催告は不要となります。
また、竹木が共有物である場合は、各共有者が越境している枝を切り取ることができるとされました(民法233条2項)。したがいまして、竹木の共有者の一人から承諾を得れば、越境された土地の所有者がその共有者に代わって枝を切り取ることができると考えられます。
所有者不明の土地が増加するにつれて、竹木の枝の処理に関する問題も増加することが考えられます。費用負担の問題もありますので、詳細は弁護士に相談することをお勧めします。

東京千代田区・文京区の小野貴朗総合法律事務所は、JR水道橋駅徒歩2分の身近な法律事務所です。
関東一円を中心に、ご相談により全国の皆様をサポートしております。
不動産トラブル(建物明渡請求、借地借家)、遺言・相続、交通事故、離婚問題から、成年後見、債権回収、企業法務まで、個人・法人を問わず幅広く対応いたします。
特に、不動産・相続・交通事故・離婚などのご相談は初回30分無料です。
公認会計士、税理士、司法書士など他士業との連携で、複雑な問題もワンストップで解決に導きます。
あなたに寄り添い、笑顔を取り戻すために全力を尽くします。
法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
【不動産】 敷金と原状回復義務について
賃貸マンションの退去時によく起きるトラブルとして、敷金と原状回復義務があります。本来、賃貸借契約においては、通常使用に伴う汚損・損耗の修繕費用は使用利益の対価である賃料によって当然に賄われていると解されています。したがって、通常使用に伴う汚損・損耗については賃借人がこれを新品同様の状態に原状回復する義務はなく、賃貸人が敷金から補填することはできないのが原則です。国土交通省住宅局が公表している「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン(再改訂版)」においても同様の考え方が示されています。
しかし、賃貸借契約書に、通常使用に伴う汚損・損耗についても賃借人が負担するという特約が付いている場合、その特約が有効となる場合があります。最高裁判例では、賃借人が補修費用を負担することになる通常損耗及び経年変化の範囲が賃貸借契約書の条項自体に具体的に明記されているか、あるいは賃貸人が口頭により説明し賃借人がその旨を明確に認識し、それを合意の内容としたなど「通常損耗補修特約」が明確に合意されている場合には、賃借人に原状回復義務が認められるとしており、賃借人が通常使用に伴う汚損・損耗について原状回復義務を負う場合があることを認めています。
原状回復ガイドラインでも同様の観点から、①特約の必要性があり、かつ暴利的でないなどの客観的、合理的理由が存在すること、②賃借人が特約によって通常の原状回復義務を超えた修繕等の義務を負うことについて認識していること、③賃借人が特約による義務負担の意思表示をしていること、の要件を満たす場合には通常損耗補修特約が有効になるとしています。
例えば、畳のすり減りや画鋲の跡(但し下地ボードの張替えが不要な程度のもの)などは賃借人が通常の生活をする上で発生するものなので通常使用に伴う汚損・損耗であり、敷金で補填することはできず、したがって、他に汚損・損耗などがなければ敷金は返還されるのが原則です。しかし、通常損耗補修特約が成立していると認められる場合には賃借人が原状回復義務を負担することになります。したがって、原状回復義務を巡ってトラブルになったときは、賃貸借契約書で原状回復義務についてどのように取り決められているかを確認する必要が出てきます。
退去の際にトラブルになるのは、賃貸人・賃借人双方にとって好ましくない事態です。賃貸人側であれば、原状回復義務の範囲について賃貸借契約書で詳細に定めておくこと(対象箇所、単位、単価などを明記する)、賃借人側であれば契約前に賃貸借契約書をよく読んで原状回復義務を負担する範囲を理解すること、負担の範囲が大きいようであれば契約しないことも考えることが重要です。

東京千代田区・文京区の小野貴朗総合法律事務所は、JR水道橋駅徒歩2分の身近な法律事務所です。
関東一円を中心に、ご相談により全国の皆様をサポートしております。
不動産トラブル(建物明渡請求、借地借家)、遺言・相続、交通事故、離婚問題から、成年後見、債権回収、企業法務まで、個人・法人を問わず幅広く対応いたします。
特に、不動産・相続・交通事故・離婚などのご相談は初回30分無料です。
公認会計士、税理士、司法書士など他士業との連携で、複雑な問題もワンストップで解決に導きます。
あなたに寄り添い、笑顔を取り戻すために全力を尽くします。
法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。