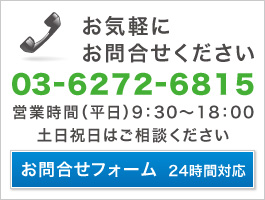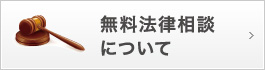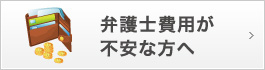【成年後見】 成年後見制度が一部改正されました~その1
認知症、知的障害その他の精神上の障害があることにより財産の管理や日常生活等に支障がある人達を社会全体で支え合うことは、高齢社会における喫緊の課題であり、かつ、共生社会の実現に資すること、及び成年後見制度はこれらの人達を支える重要な手段です。しかし、同制度が十分に利用されていないことに鑑み、「成年後見制度の利用の促進に関する法律」が成立し、平成28年4月15日に公布、同年5月13日に施行となりました。
この法律では、その基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、基本方針その他の基本となる事項を定めるとともに、成年後見制度利用促進会議及び成年後見制度利用促進委員会を設置すること等により、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することが目的とされました。
また、これに関連して、「成年後見の事務の円滑化を図るための民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」が成立しました。この法律は、平成28年4月13日に公布され、施行期日は同年10月13日となっています。この法律により、成年後見人の事務に関して、成年被後見人宛の郵便物に関する取扱いや、成年被後見人が亡くなった場合の相続財産に関する取扱い等が改正されました。本コラムでは、前者についてご説明いたします。
成年被後見人宛の郵便物の中には、株式の配当通知や金融機関からの通知などが含まれていることがあり、これらは、成年被後見人の財産状況の把握や財産管理のための有力な資料となります。しかし、これまでは成年被後見人宛の郵便物を成年後見人宛に回送することができる旨の規定がなく、成年被後見人の財産管理に支障が生じるおそれがありました。そこで、この問題を解決するために郵便物の回送に関する規定が新設されました。
これにより、家庭裁判所は、成年後見人の申立てに基づき、信書の送達の事業を行う者に対し、期間を定めて、成年被後見人に宛てた郵便物等を成年後見人に配達すべき旨を嘱託することができるものとされました。そして、成年後見人は、回送された郵便物を開いて見ることができる旨が規定されました。
また、成年後見人は、受け取った郵便物のうち成年後見人の事務に関しないものは速やかに成年被後見人に交付しなければならないものとされ、成年被後見人は成年後見人に対し、成年後見人が受け取った郵便物の閲覧を求めることができるものとされました。
なお、嘱託の期間は6か月を超えることができないものとされていますが、これは憲法で保障されている通信の秘密に配慮したものです。
また、この規定は後見類型のみが対象とされており、保佐・補助については対象外とされています。保佐・補助の場合は、被保佐人・被補助人が郵便物について自ら相応の管理をすることができること、保佐人・補助人は家庭裁判所から与えられた代理権の行使に必要な範囲で財産管理をするものであるため、保佐・補助についてまで郵便物の回送を認めることは通信の秘密を不当に侵害することになりかねないからとされています。

東京千代田区・文京区の小野貴朗総合法律事務所は、JR水道橋駅徒歩2分の身近な法律事務所です。
関東一円を中心に、ご相談により全国の皆様をサポートしております。
不動産トラブル(建物明渡請求、借地借家)、遺言・相続、交通事故、離婚問題から、成年後見、債権回収、企業法務まで、個人・法人を問わず幅広く対応いたします。
特に、不動産・相続・交通事故・離婚などのご相談は初回30分無料です。
公認会計士、税理士、司法書士など他士業との連携で、複雑な問題もワンストップで解決に導きます。
あなたに寄り添い、笑顔を取り戻すために全力を尽くします。
法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。