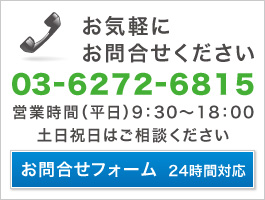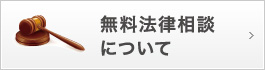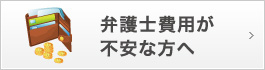Archive for the ‘相続’ Category
【相続】 預貯金債権も遺産分割の対象となりました
ニュースなどで取り上げられておりましたが、昨日最高裁判所において遺産分割における預貯金債権の取扱いに関する決定が出されました。
(全文)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/086354_hanrei.pdf
結論としては、普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象になるというものです(裁判官全員一致の意見)。
本事件では普通預金、ゆうちょ銀行の通常貯金及び定期貯金が対象となっていたことから、最高裁は、それぞれの預貯金債権について分けて検討しており、それぞれ以下の理由が挙げられています。
1.普通預金債権、通常貯金債権
・普通預金契約及び通常貯金契約は、一旦契約を締結して口座を開設すると、以後預金者がいつでも自由に預入れや払戻しをすることができる継続的取引契約であり、口座に入金が行われるたびにその額についての消費寄託契約が成立するが、その結果発生した預貯金債権は、口座の既存の預貯金債権と合算され、1個の預貯金債権として扱われるものであること
・このように、普通預金債権、通常貯金債権は、いずれも1個の債権として同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものであり、この理は預金者が死亡した場合においても異ならないこと
・これらの債権は口座において管理されており、預貯金契約上の地位を準共有する共同相続人が全員で預貯金契約を解約しない限り、同一性を保持しながら常にその残高が変動し得るものとして存在し、各共同相続人に確定額の債権として分割されることはないと解されること
・相続開始時における各共同相続人の法定相続分相当額を算定することはできるが、預貯金契約が終了していない以上、その額は観念的なものにすぎないこと
・預貯金債権が相続開始時の残高に基づいて当然に相続分に応じて分割され、その後口座に入金が行われるたびに各共同相続人に分割されて帰属した既存の残高に、入金額を相続分に応じて分割した額を合算した預貯金債権が成立すると解することは、預貯金契約の当事者に煩雑な計算を強いるものであり、その合理的意思に反すること
2.定期貯金債権
・定期貯金の前身である定期郵便貯金につき、郵便貯金法は、一定の預入期間を定め、その期間内には払戻しをしない条件で一定の金額を一時に預入するものと定め、原則として預入期間が経過した後でなければ貯金を払い戻すことができず、例外的に預入期間内に貯金を払い戻すことができる場合には一部払戻しの取扱いをしないものと定めていること
・郵政民営化法の施行により、日本郵政公社は解散し、その行っていた銀行業務は株式会社ゆうちょ銀行に承継され、ゆうちょ銀行は、通常貯金、定額貯金等のほかに定期貯金を受け入れているところ、その基本的内容が定期郵便貯金と異なるものであることはうかがわれないから、定期貯金についても、定期郵便貯金と同様の趣旨で、契約上その分割払戻しが制限されているものと解されること
・この制限は、単なる特約ではなく定期貯金契約の要素というべきであること
・定期貯金債権が相続により分割されると解すると、それに応じた利子を含めた債権額の計算が必要になる事態を生じかねず、定期貯金に係る事務の定型化、簡素化を図るという趣旨に反すること
・仮に定期貯金債権が相続により分割されると解したとしても、同債権には上記の制限がある以上、共同相続人は共同して全額の払戻しを求めざるを得ず、単独でこれを行使する余地はないので、そのように解する意義は乏しいこと
このように、最高裁は各預貯金債権の内容及び性質から結論を導いています。この結論を導いた背景として、一般的には遺産分割においては被相続人の財産をできる限り幅広く対象とすることが望ましいこと、現金のように評価についての不確定要素が少なく、具体的な遺産分割の方法を定めるに当たっての調整に資する財産を遺産分割の対象とすることに対する要請も広く存在するところ、預貯金が現金に近いものとして想起されること、といった観点も踏まえられているようです。
今回の最高裁決定は、今までの最高裁判例(預金債権は当然に分割されるとの立場)と銀行実務の取扱い(相続人全員の同意がなければ払戻に応じない)との齟齬を修正するものとして大きな意味があるといえるでしょう。ただ、裁判官の意見において、被相続人の生前に扶養を受けていた相続人が預貯金を払い戻すことができず生活に困窮する、被相続人の入院費用や相続税の支払に窮するといった事態が生ずるおそれがあること等が指摘されています(この点に対しては、補足意見において、遺産分割の審判事件を本案とする保全処分として、例えば、特定の共同相続人の急迫の危険を防止するために、相続財産中の特定の預貯金債権を当該共同相続人に仮に取得させる仮処分等を活用することが考えられる、とされています)。
最高裁判例が出たばかりですので、今後の実務の動向等に注目していきたいと思います。

東京千代田区・文京区の小野貴朗総合法律事務所は、JR水道橋駅徒歩2分の身近な法律事務所です。
関東一円を中心に、ご相談により全国の皆様をサポートしております。
不動産トラブル(建物明渡請求、借地借家)、遺言・相続、交通事故、離婚問題から、成年後見、債権回収、企業法務まで、個人・法人を問わず幅広く対応いたします。
特に、不動産・相続・交通事故・離婚などのご相談は初回30分無料です。
公認会計士、税理士、司法書士など他士業との連携で、複雑な問題もワンストップで解決に導きます。
あなたに寄り添い、笑顔を取り戻すために全力を尽くします。
法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
【相続】 相続放棄したらそれで終わりですか?
相続放棄というのは、亡くなった人に借金があってプラスの財産より多い場合に、相続人が借金の支払いを免れるためにある制度です。相続放棄をした者は、初めから相続人とならなかったものとみなされます。
では、相続放棄をすれば、後のことは我関せずで良いのでしょうか?
民法上、相続放棄をした者は、その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで、自己の財産におけるのと同一の注意義務をもって、その財産の管理を継続しなければならないとされています。また、それと共に、相続放棄をした者には、事務処理状況の報告義務、財産の引渡義務も課せられています(民法940条)。注意義務に反する管理行為によって相続財産に損害を生じさせた場合は、その賠償責任を負います。
これは、相続財産が管理されないまま放置されてしまうと、他の相続人、次順位の相続人、相続債権者などに損害を与えるおそれがあるので、無管理状態による相続財産の滅失毀損を防止するため、相続放棄をした者に一定期間相続財産を管理する法的責任を負わせているのです。
例えば、亡くなった人が空き家を所有していた場合を想定すると分かりやすいかと思います。この場合、相続放棄したからといって空き家をほったらかしにして良いことにはなりません。
相続放棄をした者は、他の相続人(同順位の相続人がいない場合は次順位の相続人)に空き家の管理を始めてもらうため速やかに連絡して引き継いでもらう必要があります。それまでの間は空き家を管理しなければなりません。
次順位の相続人も相続放棄して相続人が不存在となる場合には、相続財産の管理人が選任されて職務を開始するまで相続放棄をした者の管理義務が継続しますので、相続財産管理人の選任申立てを検討する必要があるでしょう。
なお、相続放棄をした者と第三者との関係についてはどうでしょうか。例えば、前記の事例で、管理不十分のため空き家が倒壊して隣家に損害を与えた場合です。隣家の人が管理義務違反を理由に損害賠償請求してくることが考えられます。
この場合、民法940条が第三者との関係でも根拠条文になるかははっきりしないように思うのですが(民法940条の趣旨が、他の相続人や相続債権者の保護を目的としていることや、民法940条が準用する委任規定における委任者が相続人と解されているため)、第三者との関係では不法行為責任(民法709条、民法717条)を負う可能性が考えられますので、いずれにせよ結論として損害賠償責任を負う可能性があることに変わりはないように思われます(個人的な見解です)。
相続放棄は大変ありがたい制度ですが、相続放棄して一件落着で終わらない場合があります。相続財産の内容などを吟味する必要がありますので、判断に迷ったときは弁護士にご相談ください。

東京千代田区・文京区の小野貴朗総合法律事務所は、JR水道橋駅徒歩2分の身近な法律事務所です。
関東一円を中心に、ご相談により全国の皆様をサポートしております。
不動産トラブル(建物明渡請求、借地借家)、遺言・相続、交通事故、離婚問題から、成年後見、債権回収、企業法務まで、個人・法人を問わず幅広く対応いたします。
特に、不動産・相続・交通事故・離婚などのご相談は初回30分無料です。
公認会計士、税理士、司法書士など他士業との連携で、複雑な問題もワンストップで解決に導きます。
あなたに寄り添い、笑顔を取り戻すために全力を尽くします。
法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
【相続】 遺留分の放棄について
遺留分とは、一定の相続人のために、相続に際して法律上取得することが保障されている遺産の一定割合のことをいい、遺族の生活保障といった観点から認められています。遺留分権利者は、兄弟姉妹を除く法定相続人(配偶者・子・直系尊属)です。
この遺留分を侵害した贈与や遺贈などは法律上当然に無効となるわけではありませんが、遺留分権利者が減殺請求をした場合、その遺留分を侵害する限度で効力を失うことになります。
他方、この遺留分は放棄することもできます。相続が発生した後においては、遺留分を放棄することは自由です。これに対して、相続開始前に遺留分を放棄するには家庭裁判所の許可が必要です。
家庭裁判所の許可を得るためには、遺留分権を有する相続人が、被相続人の住所地を管轄する家庭裁判所に対して、遺留分放棄の許可審判申立てをします。
家庭裁判所の許可基準としては、①遺留分権利者の自由意思に基づくこと、②放棄理由の合理性・必要性・代償性が挙げられており、事案に応じた判断になります。
なお、司法統計によると、全家庭裁判所における遺留分放棄の許可審判申立てについて、
・平成27年度は、既済総数1152件のうちの1076件が認容
・平成26年度は、既済総数1193件のうちの1135件が認容
となっており、9割以上が認容となっています。
遺留分放棄許可の審判があると、申立てをした相続人の遺留分権はなくなります。しかし、相続人でなくなったわけではありません。被相続人としては自己の財産を自由に処分できるようにしておくのが目的でしょうから、別途遺言書を作成して自己の財産の処分について取り決めておく必要があります。
また、遺留分を放棄したからといって債務が承継されないことにはならないので、仮に債務を承継したくない場合は、相続放棄の手続を取る必要があります。
遺留分放棄の許可審判申立てをする場合、許可基準に合致する事実関係を拾い上げて申立書に反映させていく必要があります。遺留分放棄について検討されている方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

東京千代田区・文京区の小野貴朗総合法律事務所は、JR水道橋駅徒歩2分の身近な法律事務所です。
関東一円を中心に、ご相談により全国の皆様をサポートしております。
不動産トラブル(建物明渡請求、借地借家)、遺言・相続、交通事故、離婚問題から、成年後見、債権回収、企業法務まで、個人・法人を問わず幅広く対応いたします。
特に、不動産・相続・交通事故・離婚などのご相談は初回30分無料です。
公認会計士、税理士、司法書士など他士業との連携で、複雑な問題もワンストップで解決に導きます。
あなたに寄り添い、笑顔を取り戻すために全力を尽くします。
法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
【相続】 自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為
遺言者が故意に遺言書を破棄したときは、その破棄した部分については遺言を撤回したものとみなすとされています(民法1024条前段)。一般的には、遺言書を焼却、切断したときなどがこれに該当するとされています。
では、遺言者が自筆証書遺言である遺言書の文面全体に故意に斜線を引いた場合、遺言書を破棄したときに該当するとして遺言を撤回したものとみなされるのでしょうか。
民法は、遺言書の内容を変更する場合、遺言者がその場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に押印しなければ変更の効力が生じないと規定しています(民法968条2項)。
そこで、遺言書に斜線を引いた場合、元の文字が判読できるため、遺言書の「破棄」ではなく「変更」に当たるものの、上記変更の方式に従っていないため変更の効力が認められず、遺言は元の文面のものとして有効となるのではないかが問題になります。
この点について、近時、最高裁判所が遺言書の破棄に当たると判断しましたので、ご紹介します(最高裁平成27年11月20日判決)。
以下、判決文の引用です。
「・・・民法は,自筆証書である遺言書に改変等を加える行為について,それが遺言書中の加除その他の変更に当たる場合には,968条2項所定の厳格な方式を遵守したときに限って変更としての効力を認める一方で,それが遺言書の破棄に当たる場合には,遺言者がそれを故意に行ったときにその破棄した部分について遺言を撤回したものとみなすこととしている(1024条前段)。そして,前者は,遺言の効力を維持することを前提に遺言書の一部を変更する場合を想定した規定であるから,遺言書の一部を抹消した後にもなお元の文字が判読できる状態であれば,民法968条2項所定の方式を具備していない限り,抹消としての効力を否定するという判断もあり得よう。ところが,本件のように赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は,その行為の有する一般的な意味に照らして,その遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当であるから,その行為の効力について,一部の抹消の場合と同様に判断することはできない。
以上によれば,本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は,民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するというべきであり,これによりA(筆者注・遺言者のことです)は本件遺言を撤回したものとみなされることになる。したがって,本件遺言は,効力を有しない。」
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/488/085488_hanrei.pdf
このように最高裁は遺言書の破棄に当たると判示しましたが、遺言者が故意に赤色ボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引いた(文面全体の左上から右下にかけて赤色のボールペンで1本の斜線が引かれていたようです)という事実関係の下での判断です。
ご自身が亡くなった後の相続人間の無用な対立を防ぐため、自筆証書による遺言書の内容を変更する場合は、民法所定の変更の方式に従って遺言書を変更するか、改めて遺言書を書き直して古い遺言書はシュレッダーで処分するなど、疑義を残さない遺言書にしておきたいものです。

東京千代田区・文京区の小野貴朗総合法律事務所は、JR水道橋駅徒歩2分の身近な法律事務所です。
関東一円を中心に、ご相談により全国の皆様をサポートしております。
不動産トラブル(建物明渡請求、借地借家)、遺言・相続、交通事故、離婚問題から、成年後見、債権回収、企業法務まで、個人・法人を問わず幅広く対応いたします。
特に、不動産・相続・交通事故・離婚などのご相談は初回30分無料です。
公認会計士、税理士、司法書士など他士業との連携で、複雑な問題もワンストップで解決に導きます。
あなたに寄り添い、笑顔を取り戻すために全力を尽くします。
法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
【相続】 花押による自筆証書遺言は無効
自筆証書遺言(紙とペンを用意して紙に遺言を書くというように、遺言書というとまず思い浮かぶ遺言の作成方法です)をする場合には、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならないとされています(民法968条1項)。
この自筆証書遺言への押印に関して、近時、最高裁判所が、花押による自筆証書遺言は無効との判断をしましたので、ご紹介します(最高裁平成28年6月3日判決)。
以下、判決文の引用です。
「・・・花押を書くことは,印章による押印とは異なるから,民法968条1項の押印の要件を満たすものであると直ちにいうことはできない。そして,民法968条1項が,自筆証書遺言の方式として,遺言の全文,日付及び氏名の自書のほかに,押印をも要するとした趣旨は,遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるという我が国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ(最高裁昭和62年(オ)第1137号平成元年2月16日第一小法廷判決・民集43巻2号45頁参照),我が国において,印章による押印に代えて花押を書くことによって文書を完成させるという慣行ないし法意識が存するものとは認め難い。以上によれば,花押を書くことは,印章による押印と同視することはできず,民法968条1項の押印の要件を満たさないというべきである。」http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/930/085930_hanrei.pdf
自筆証書遺言が有効になる要件は民法で決まっており、また、加除訂正する場合もその方法が決まっています。せっかくご自身で遺言書を作成しても法律の要件を満たさないために無効になってしまう場合もありますので、遺言書を作成される場合は、弁護士にご相談ください。

東京千代田区・文京区の小野貴朗総合法律事務所は、JR水道橋駅徒歩2分の身近な法律事務所です。
関東一円を中心に、ご相談により全国の皆様をサポートしております。
不動産トラブル(建物明渡請求、借地借家)、遺言・相続、交通事故、離婚問題から、成年後見、債権回収、企業法務まで、個人・法人を問わず幅広く対応いたします。
特に、不動産・相続・交通事故・離婚などのご相談は初回30分無料です。
公認会計士、税理士、司法書士など他士業との連携で、複雑な問題もワンストップで解決に導きます。
あなたに寄り添い、笑顔を取り戻すために全力を尽くします。
法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
【相続】 相続分はどのくらい?
遺産分割を行うためには、相続人間で遺産をどのような割合で分割するか(相続分)が決まっていなければなりません。相続分について被相続人が遺言で何ら意思を表明していなかった場合のために、民法は、以下のとおり相続分を定めています(法定相続分)。
1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1
2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1
3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は4分の3、兄弟姉妹の相続分は4分の1
従前、嫡出でない子の相続分は嫡出子の相続分の2分の1と定められていましたが(民法900条4号ただし書)、平成25年9月4日の最高裁決定により同規定は憲法14条1項(法の下の平等)に違反していると判断されました。これにより、最高裁決定の翌日である平成25年9月5日以後に開始した相続については、嫡出でない子と嫡出子の相続分は同等のものとして扱われます。
なお、最高裁は、従前の規定は遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判示しましたが、この違憲判断は、平成13年7月1日から平成25年9月4日までに相続が開始した他の事案につき、従前の規定を前提としてされた遺産分割の審判その他の裁判、遺産分割協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものではない旨判示しています。したがいまして、そのように確定的なものとなった事案については、最高裁決定によっても効力は覆りません。
また、昭和55年改正前の民法では、上記1については子の相続分は3分の2、配偶者の相続分は3分の1、上記2については配偶者と直系尊属の相続分は各2分の1、上記3については配偶者の相続分は3分の2、兄弟姉妹の相続分は3分の1とされており、現在の規定とは異なっておりました。この民法改正は、配偶者の地位の強化という観点から行われたものです。
この民法改正は昭和56年1月1日から施行されましたので、昭和55年12月31日以前の相続については旧法が適用されます。被相続人の死亡が昭和55年12月31日以前の遺産分割事件は現在でもあり得ますので(遺産分割が長年放置されていた場合)、この場合、法定相続分には留意する必要があります。

東京千代田区・文京区の小野貴朗総合法律事務所は、JR水道橋駅徒歩2分の身近な法律事務所です。
関東一円を中心に、ご相談により全国の皆様をサポートしております。
不動産トラブル(建物明渡請求、借地借家)、遺言・相続、交通事故、離婚問題から、成年後見、債権回収、企業法務まで、個人・法人を問わず幅広く対応いたします。
特に、不動産・相続・交通事故・離婚などのご相談は初回30分無料です。
公認会計士、税理士、司法書士など他士業との連携で、複雑な問題もワンストップで解決に導きます。
あなたに寄り添い、笑顔を取り戻すために全力を尽くします。
法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
【相続】 遺言書には自分の思いも残せます
遺言書はお金がたくさんある人が書くものと思われている方も多いかもしれません。しかし、遺言書には自分の財産の分け方を記すだけでなく、相続人に対する自分の思いを残すことができるという意外なメリットもあります。
付言事項と言いますが、自分の死後に相続人に届く手紙と言ったら分かりやすいでしょうか。たとえ相続人が子ども一人でも良いのです。
子どもにしてみれば「今さらなぜ遺言書?」と思うかもしれませんが、遺言書に子どもに対する感謝の気持ちなど、生前には恥ずかしくて面と向かって言えなかったことが書かれていたら、子どもはどんなに喜ぶでしょう。親から子への感謝の気持ちは、不動産や預金よりも大事なプレゼントです。子どもにとっても今後の生きる糧になるはずです。
付言事項は大事です。一言でもいいのです。あなたのメッセージを残してみてはいかがでしょうか。

東京千代田区・文京区の小野貴朗総合法律事務所は、JR水道橋駅徒歩2分の身近な法律事務所です。
関東一円を中心に、ご相談により全国の皆様をサポートしております。
不動産トラブル(建物明渡請求、借地借家)、遺言・相続、交通事故、離婚問題から、成年後見、債権回収、企業法務まで、個人・法人を問わず幅広く対応いたします。
特に、不動産・相続・交通事故・離婚などのご相談は初回30分無料です。
公認会計士、税理士、司法書士など他士業との連携で、複雑な問題もワンストップで解決に導きます。
あなたに寄り添い、笑顔を取り戻すために全力を尽くします。
法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
【相続】 相続に関する相談会を実施します(11月25日)
平成27年1月1日に税制改正が行われたこともあり、相続はより一層身近な問題になりました。自分の思いを残すこと、そして家族の争いを防ぐため、相続についての心配事を相談してみませんか。税理士、行政書士と共同で実施しますので、相続税、遺言書の書き方、エンディングノート、相続手続代行、遺産分割協議・調停など、相続に関する各種のご相談に対応が可能です。
開催日時、場所は以下のとおりです。相談料は無料です。
当日直接会場にお越しいただければ相談可能ですが、事前の予約も承ります。詳細は当事務所までお気軽にお問い合わせください。
日時:平成27年11月25日(水)10:00~16:00
場所:文京春日郵便局(文京シビックセンター1階です)

東京千代田区・文京区の小野貴朗総合法律事務所は、JR水道橋駅徒歩2分の身近な法律事務所です。
関東一円を中心に、ご相談により全国の皆様をサポートしております。
不動産トラブル(建物明渡請求、借地借家)、遺言・相続、交通事故、離婚問題から、成年後見、債権回収、企業法務まで、個人・法人を問わず幅広く対応いたします。
特に、不動産・相続・交通事故・離婚などのご相談は初回30分無料です。
公認会計士、税理士、司法書士など他士業との連携で、複雑な問題もワンストップで解決に導きます。
あなたに寄り添い、笑顔を取り戻すために全力を尽くします。
法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。
【相続】 相続が開始したら誰が相続人になるかを確認する
ある人が亡くなり相続が発生した場合(亡くなった人のことを「被相続人」といいます)、まず誰が相続人になるかを確認する必要があります。民法は、以下の者が相続人になるとしています。
・被相続人の子(第1順位)
・被相続人の直系尊属(第2順位)
・被相続人の兄弟姉妹(第3順位)
・被相続人の配偶者
順番に見ていきましょう。
まず、被相続人の子は第1順位の相続人となります。被相続人の子が相続の開始前に死亡していた場合は、その者の子が相続人となります(代襲相続)。つまり、孫が相続人になるということです。孫も死亡していた場合は曾孫が相続人になる(再代襲相続)というように、繰り返し代襲相続が行われることになります。
被相続人に子(子が死亡している場合は孫など)がいない場合は、被相続人の直系尊属が第2順位の相続人になります。被相続人の父母、祖父母、曾祖父母が直系尊属に該当します。
直系尊属全員が相続人になるわけではなく、親等の近い者だけが相続人となります。つまり、父母、祖父母、曾祖父母のいずれもが生存しているときは父母だけが共同相続人となります。祖父母は父母の双方が死亡しているときにはじめて相続人となります。
相続開始時に母が生存、父が死亡、しかし亡父の父母は生存しているという場合は、被相続人に親等の近い母のみが相続人となります。
第1順位、第2順位の相続人がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
兄弟姉妹の場合も代襲相続が認められています。即ち、兄弟姉妹が相続開始以前に死亡していた場合は、その者の子が代襲相続人となります。つまり甥・姪が相続人になるということです。しかし、子の代襲相続と異なり再代襲相続は認められていないので、甥・姪の子は相続人とはなりません。
かつては兄弟姉妹の再代襲も認められていましたが、相続人が50人を超える例も生じたといわれており、相続を巡る法律関係が極めて複雑化するため昭和55年に改正されました。
そして、被相続人の配偶者は常に相続人となります。第1順位から第3順位までのいずれかの相続人がいる場合は、これらの相続人と共に共同相続人となります。
相続においては、相続欠格、廃除、相続放棄が生じた場合なども誰が相続人になるかを検討する必要があります。誰が相続人になるかは個別のケースに応じて異なってきますので、詳しくはお気軽にご相談ください。

東京千代田区・文京区の小野貴朗総合法律事務所は、JR水道橋駅徒歩2分の身近な法律事務所です。
関東一円を中心に、ご相談により全国の皆様をサポートしております。
不動産トラブル(建物明渡請求、借地借家)、遺言・相続、交通事故、離婚問題から、成年後見、債権回収、企業法務まで、個人・法人を問わず幅広く対応いたします。
特に、不動産・相続・交通事故・離婚などのご相談は初回30分無料です。
公認会計士、税理士、司法書士など他士業との連携で、複雑な問題もワンストップで解決に導きます。
あなたに寄り添い、笑顔を取り戻すために全力を尽くします。
法律問題でお困りの際は、一人で悩まず、まずはお気軽にお問い合わせください。